育児・介護休業法の改正されます・前編
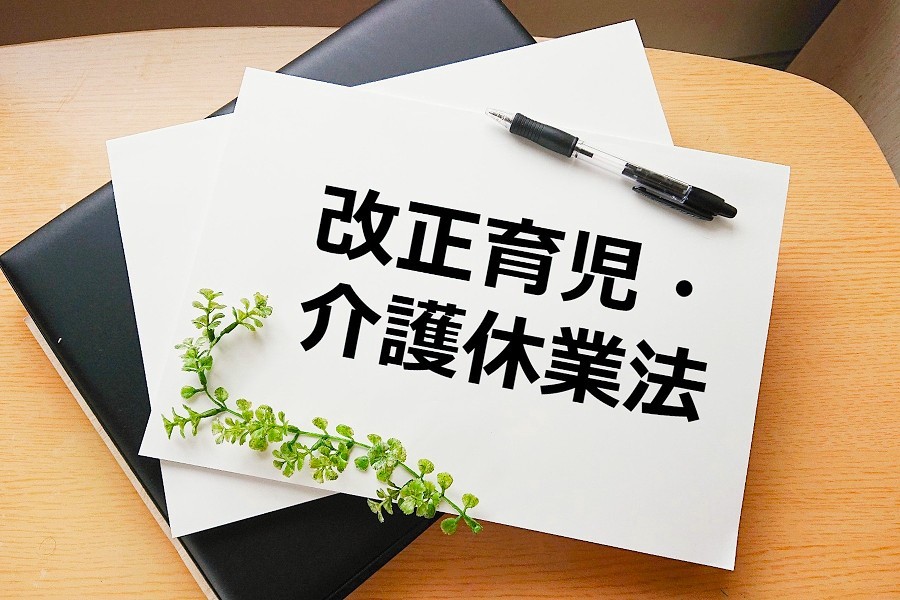
2024年5月に育児介護休業法等の改正法が国会で可決・成立し、2025年4月1日より段階的な施行が予定されています。育児介護休業法の今までの改正の流れと育児介護休業法について解説します。
これまでの改正内容
育児介護休業法の正式名称は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」です。育児や介護を行う人を支援して仕事と家庭の両立を目的にした法律です。
これまでの改正の内容をご紹介します。
▢ 1990年代~
- 1992年 4月1日に育児休業法の施行
『育児休業等に関する法律(通称は、「育児休業法」)』が施行されました。 - 1995年 4月1日に育児休業法が改正され育児・介護休業法になる
新たに介護休業制度が創設されたことにより、法律の名称が、現名称の「育児・介護休業法」に変更されました。 - 1999年4月1日の改正
介護休業の義務化と深夜業の制限制度の創設されました。
▢ 2000年代~
- 2002年 4月1日の改正
子の看護休暇の創設(努力義務)/ 時間外労働の制限制度の創設 / 短時間勤務措置の対象年齢の引き上げ / 転勤への配慮など - 2005年 4月1日の改正
子の看護休暇の義務化 / 育児休業期間の延長 / 有期雇用労働者への適用拡大 / 介護休業の取得回数制限の緩和
▢ 2010年代~
- 2010年 6月30日の改正
パパ・ママ育休プラスの創設・パパ休暇の創設 / 所定外労働の免除制度の創設 / 短時間勤務措置の内容変更 / 子の看護休暇の付与日数の変更 / 介護休暇制度の創設 / 配偶者が専業主婦(夫)である場合の除外規定を廃止 / 法違反に対する企業名の公表制度と過料の創設 - 2017年 1月1日の改正
介護休業の分割取得 / 介護のための所定労働時間の短縮措置の拡大 / 介護のための所定外労働の制限 / 子の看護休暇・介護休暇の半日単位の取得 / 有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件の緩和 / 育児休業の対象となる子の範囲の見直し / マタハラ・パタハラなどの防止措置義務 - 2017(平成29)年 10月1日の改正
最長2歳まで育児休業の再延長が可能 / 育児休業制度の個別周知(努力義務)/ 育児目的休暇の導入促進(努力義務)
▢ 2020年代~
- 2021(令和3)年 1月1日の改正
子の看護休暇・介護休暇の1時間単位の取得 / 子の看護休暇・介護休暇を取得できる対象者の拡大 - 2022(令和4)年 4月1日の改正
雇用環境の整備・育児休業制度の周知・育児休業の取得意向の確認の義務化 / 有期雇用労働者の育児休業の取得要件の緩和 - 2022(令和4)年 10月1日の改正
出生時育児休業制度の創設 / パパ休暇制度の廃止 / 育児休業の分割取得 - 2023(令和5)年 4月1日の改正
育児休業の取得状況の公表義務 / 法改正により、常時雇用する従業員数が1,000人を超える会社は、育児休業の取得状況を公表を義務付けられました。
労働者・経営者に与える影響
柔軟な働き方の実現として育児や介護を行う労働者は、テレワークや短時間勤務制度などを利用しやすくなり、仕事と家庭生活の両立がしやすくなります。子の看護休暇や介護休暇の取得が容易になり、必要な時に休暇を取得できる環境が整備されます。また、育児や介護のための休暇や柔軟な勤務制度を利用することで、労働者の精神的・身体的負担が軽減され、健康維持やストレスの軽減に寄与します。さらに育児や介護のために仕事を辞める必要がなくなり、キャリアの継続が可能になります。これにより、長期的なキャリア形成が支援されます。
経営者は改正内容に基づき、就業規則の見直しや労使協定の締結が必要となります。これにより、企業は法令遵守のための対応を求められます。育児休業や介護休業の取得状況の公表義務が拡大され、従業員数300人超の企業は毎年公表する必要があります。育児や介護を行う従業員が働きやすい環境を整備することで、従業員の満足度やモチベーションが向上し、離職率の低下が期待されます。柔軟な働き方を導入することで、優秀な人材の確保や定着が促進されます。育児休業や介護休業の取得により、一時的に人員不足が発生する可能性があります。これに対する対応策として、代替要員の確保や業務の見直しが必要となります。
2025年4月法改正‐育児休業について
- 残業免除の対象拡大: 請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることができる対象の範囲が、「3歳に満たない子を養育する労働者」から、「小学校就学前の子を養育する労働者」まで拡大
- 育児のためのテレワーク導入の努力義務化: 3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化される
- 子の看護休暇の制度変更・対象拡大: 対象となる子の範囲が、「小学校就学の始期に達するまで」⇒「小学校3年生修了まで」に延長され、休暇の取得事由に、「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園・入学式、卒園式」も対象
- 育児休業取得に関する状況把握・数値目標設定の義務化
- 男性の育児休業取得状況の公表義務の対象拡大
- 出生後休業支援給付の創設
- 出生後休業支援給付の創設
- 育児時短就業給付の創設: 被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給
- 育児休業給付金の支給期間延長手続の厳格化
2025年10月法改正‐育児休業については、3歳以上~小学校就学前の子を養育する労働者に対する柔軟な働き方を実現するための措置の義務化となり、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化として、妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の周知・意向聴取・配慮が事業主に義務化されます。2025年4月法改正‐介護休業は、介護離職防止の為の各種措置の義務化、介護休暇の対象拡大、介護離職防止の為の各種措置の義務化となります。
上記法改正のポイントは、Fukushima Ricopy Fair 2025 株式会社YACコンサルティング YAC社会保険労務士法人様 資料より引用し情報を掲載しています。福島リコピー開催の各種フェアでは、お客様への有効な情報をお届けしております。
